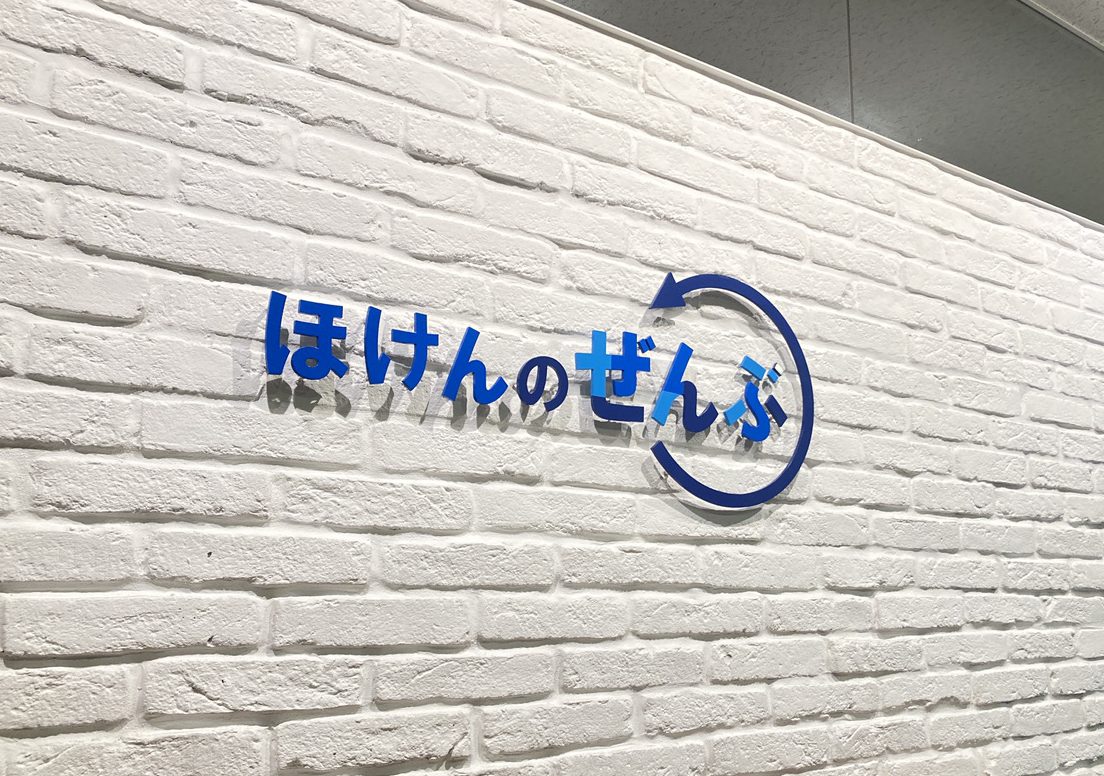「花物語」ブランドの認知症グループホームや、「花珠の家」ブランドの介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホームを展開する日本アメニティライフ協会。介護事業のほか、日本語教育や外国人就労支援なども手掛けています。
多拠点を運営する同社ならではの健康管理体制の課題や、介護業界特有の健康課題、職場づくりについて伺いました。
| 亀井様:平成27年に日本アメニティライフ協会へ入社。施設長、エリア長を経て、本部へ異動となり、現在は管理部部長として総務課も担当。 重様: 平成29年に日本アメニティライフ協会へ入社。入社から総務課一筋にて現在は社会保険関連や安全衛生関連の業務をご担当。 |
産業医との「横連携」、健診代行による「業務効率化」を実現
職員の健康管理をするうえで課題になっていたことはありますか?
亀井様:当社は、東京都・神奈川県で約400の介護施設を展開し、8,000人を超える職員が働いています。規模の大きさから、全社で方針や施策を統一し、横展開していくことに難しさを感じていました。
重様:特に健康診断の管理業務は、予約受付や変更対応、健診機関の請求書処理など、外部との調整から事務作業まで、工数が多く非常に煩雑でした。健診対象者が3,000人を超えたあたりから、本部の担当者だけで調整を行うことが難しくなり、ミライトの健診予約代行サービスを導入しました。
健診予約代行サービスの導入で、業務負担の課題は解決されましたか?
重様:はい、業務負担が大幅に軽減しました。予約の手配業務だけでなく、結果の集約や労働基準監督署への報告まで対応していただける点が助かっています。
導入の背景には、職員にとってどのような受診方法が利用しやすいのかを比較検討したいという狙いもありました。
以前は対象者一人ひとりからの予約日時を本部で受けて、指定の医療機関に本部が予約を入れていました。現在は、日勤のみの職員は巡回健診を実施し、夜勤がある職員は各自でネット予約をして、医療機関を自由に選べる形式にしています。
特定業務従事者に該当する夜勤者は、年に2回受診しないといけないのですが、夜勤明けに指定の医療機関に受診しにいくのはハードルが高く、受診率が課題になっていました。
ネット予約だと提携医療機関の選択肢が多く、自宅や各事業所から好アクセスな医療機関を選べるので、受診しやすくなっているのではないかと感じています。
ネット予約の導入当初は、受診できる医療機関が少ないエリアもありましたが、担当者の方に相談したところ、迅速に提携医療機関を増やしていただきました。
職員の働き方に合わせて最適な受診方法を模索できる点が健診予約代行サービスの魅力だと感じています。
産業医紹介サービスの導入後はどのような変化がありましたか?
亀井様:拠点間の「横連携」が強化された点が大きな変化です。産業医導入前は、BCP(事業継続計画)や感染症対策の方法が施設ごとに異なっていました。一人の産業医の先生に複数の施設を担当していただくことで、各施設で連携を取りつつルールを標準化できるようになりました。
また、職場巡視によって現場の職員だけでは気づきにくいリスクを指摘していただける点も助かっています。例えば、「表面上はきれいでも、掃除が隅々まで行き届いていないと感染症のリスクが高まる」といったアドバイスをいただき、すぐに改善を行いました。
産業医の先生が定期的に訪問してくれることで、「前回指摘されたことを改善しておかなければいけない」と、問題を放置せず、早期対応する習慣がつくようになっています。 「すぐに相談できる安心感」が生まれたことも大きな効果ですね。いつもと様子が違う職員を見かけたら「次の訪問時に先生に相談してみよう」と慌てずに対応できるので、専門的な立場からアドバイスをしてもらえる存在が身近にいるのは、現場の精神的な支えになっています
エムステージの産業医紹介サービスを選んだ決め手があれば教えてください。
亀井様:初めて産業医を導入するにあたって、複数社を比較検討しましたが、エムステージの担当者の方の説明が非常に丁寧でした。衛生委員会の立ち上げ方や、産業医の先生とどのようにやり取りをするのかなど、導入後のイメージが具体的に湧いたことが大きな決め手です。
また、選任届の提出など、煩雑な手続きをサポートしていただけた点も大変助かりました。
「無理な体の動かし方をしないように」研修や現場の声かけで腰痛を防止

職員の方の健康課題について教えてください。
重様:身体介助に伴う腰痛が多い傾向にあります。そのほかにも、膝、肘の痛みを抱える職員もいますね。車椅子や、移乗ボードなどもありますが、そのような専用器具を使わない作業は身体への負担が大きいです。特に夏場の湿度が高い浴室での入浴介助や、何十人ものシーツ交換はかなりの重労働です。
亀井様: 高齢の職員も多いため、加齢に伴う身体機能の変化も考慮しながら、安全に働ける環境づくりが重要だと考えています。
腰痛対策として気をつけていることはありますか?
重様:腰痛が起こりやすい場面と対策をまとめた資料を作成し、定期的に各施設の管理職へ配布しています。そして、現場の職員一人ひとりへ周知して意識を促しています。
亀井様:腰痛が発生するケースでよくあるのが、限られた時間で業務を終わらせなければならないという焦りから、無理な姿勢で介助してしまうことです。他のスタッフが忙しそうにしていると、サポートを頼むことを遠慮してしまい、1人でやろうと無理をして痛みが生じるというケースです。
そのため、技術的な研修だけでなく「お互いに助け合った方が結果的に安全で効率も上がる」「無理をすれば、後で自分自身の身体に負担が返ってくる」といった意識付けを、研修などを通じて繰り返し伝えています。
「言語の壁」を超えて支え合う文化を醸成。多角的なサポートで外国人職員と共助する職場づくり
介護業界全体の課題でもある人手不足の解消のため、外国人職員の雇用を促進されていますが、ともに働く上での課題はありますか?
亀井様:やはり「言語の壁」によるコミュニケーションが課題になりやすいですね。来日前に日本語を学んだ技能実習生や特定技能の方に来ていただいていますが、学校で習う言葉と実際の現場で使われる言葉にはギャップがあります。例えば、介護現場での専門用語や、感情の機微を伝える細やかな表現などは理解に時間がかかり、介護記録の引き継ぎなどで戸惑うことがあるようです。
コミュニケーションを円滑にするための工夫はありますか?
亀井様:優しい日本語で書かれた書籍を紹介したり、研修動画を多言語に翻訳して提供したりといったサポートを進めています。さらに、本社に外国籍の職員が常駐する相談窓口を設け、母国語で相談できる体制も構築しました。
ただ、実際は現場でともに働く中で自然と解消されていくことが多いようです。介護業界は人手不足という課題があるので、その中で外国人職員の方は貴重な戦力です。そのため、職員の間には「一緒に働いてくれてありがたい」という感謝の気持ちが自然と根付いています。言葉の壁など、不得手な部分はお互いに支え合いながら、一緒に仕事を進めていく中で解消していく。そうした協力体制が、当社の特徴だと感じています。
職員の健康保持増進のため、健診体制と産業医連携を一層強化していきたい
産業保健活動について今後取り組んでいきたいことがあれば教えてください。
重様:職員が健診を受けやすい仕組みをさらに強化していきたいです。特に夜勤者は年に2回健診を受ける必要があるので、職員の負担にならないよう、最適な受診期間の設定などを試行錯誤しているところです。健診予約代行サービスは受診期間の設定も柔軟に対応してもらえるので、相談しながら改善を進めていきたいと考えています。
亀井様:産業医の先生方との連携をより一層深めていきたいです。職員数が多いため、現状では健康診断後の就業に関する医師の意見聴取などの個別対応に、時間を要している現状があります。
今後、定型的な業務をより効率化することで、産業医の先生方には、より専門的な視点での職場環境改善提案や、不調者の未然防止・早期対応などのサポートをしていただきたいです。そして、組織全体の健康レベルをさらに引き上げていきたいと考えています。