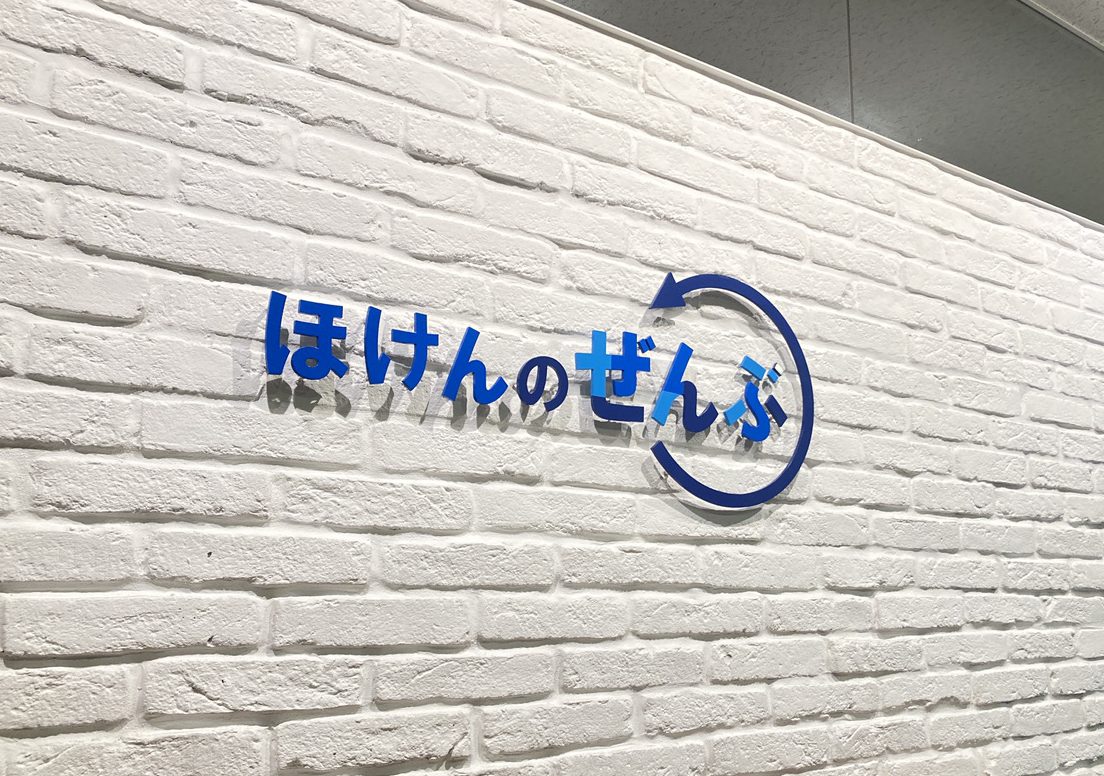小田急グループ各社の経理、人事業務を担う株式会社小田急フィナンシャルセンター。従業員同士のコミュニケーション活性化を目的とした職場環境改善のお取り組みや、ストレスチェックツール『Co-Labo』、メンタルヘルス・ヘルスケア研修サービスについて、総務部の林様、矢崎様にお話をお伺いしました。
| 林 昌史様:新卒で入社後、業務部に配属され、現在は総務部にて人事・総務・経理全般に従事。ストレスチェック制度の義務化当初よりストレスチェックをご担当。 矢崎 志穂様:新卒で入社後、業務部に10年以上在籍した後、産休・育休を経て2024年度より総務部で人事系の業務全般をご担当。 |
不調が発生したらすぐに声をあげられる環境を整備

貴社の事業内容について教えてください。
林様:弊社は、小田急グループ各社の経理や給与計算といった業務を専門的に請け負うシェアードサービスを提供しています。
担当会社の月次決算や給与計算などを担う「シェアードサービス部」と、グループ全体の業務プロセス改善や、システム導入などのコンサルティングをプロジェクト単位で行う「ビジネスサービス部」に分かれています。
担当会社は必ず複数名のチーム制を採っており、業務の属人化を防ぐ体制を整えています。経理業務では四半期決算の時期、人事業務では年末調整の時期が主な繁忙期となります。
現在、どのような健康課題がありますか?
林様:弊社の従業員は20代、30代が多く、平均年齢も32歳と比較的若い組織です。そのため、健康診断での有所見者の割合はグループ他社と比較しても少ない傾向にあります。
しかし、デスクワークが多いため、頭痛や肩こり、腰痛など、健康診断結果には現れにくい不調の声が聞かれます。また、繁忙期には運動不足や睡眠不足による不調が現れやすいようです。
多少の不調があっても、若いうちは健康について危機感を持ちづらく、「自分はまだ大丈夫」と信じ込んでいる従業員が多いと思います。しかし、慢性的な身体の痛みはパフォーマンス低下につながりますし、運動不足や睡眠不足は将来的に生活習慣病の発症が懸念されます。会社として運動促進や生活習慣改善のサポートになるような取り組みが必要だと考え、最近では福利厚生として食事補助制度を導入しはじめました。
また、業務内容や役割の変化がきっかけとなり、メンタルヘルス不調を引き起こすケースがあります。
メンタルヘルス不調のキャッチアップやフォローはどのようにされていますか?
林様:ストレスチェックで高ストレス者と判定された従業員に産業医面談を勧奨したり、長時間残業の従業員にはまずは総務部で個別面談を設定し、状況次第で産業医面談へ繋いだりしています。また、上司との定期的な1on1ミーティングで、気になる様子の部下がいる場合、上司から総務部に相談が寄せられます。
コロナ禍以降、世間的な傾向として「心身の不調を感じたら無理をせずに休むべき」「つらい時は声をあげていいんだ」という雰囲気が醸成されているように感じています。
弊社としても、従業員にいきいきと長く健康な状態で働いてもらうためにも、不調が発生したらすぐに相談ができる環境や、休復職制度を整えています。不調が起きてからだけではなく、未然にどう防止していくのか、が現状の課題です。
オフィス環境の改善で「対話」と「気づき」が増える組織へ

本社移転に伴い、オフィスレイアウトを一新したと伺いましたが、どのような経緯だったのでしょうか。
林様:社内コミュニケーションを活性化したいという思いからオフィスレイアウトを一新しました。移転前は部署ごとにフロアが分かれており、席も固定されていました。そのため、チーム内の会話はあっても、チーム外のメンバーとの交流が希薄になりやすいことが課題でした。そこで、本社移転を機に、コミュニケーションの活性化を目的としたレイアウト変更を行いました。
どのようなオフィス環境の改善を行ったのでしょうか。
林様:まず、全社でフリーアドレスを導入しました。さらに、集中したいときに使える個別ブースや、チームで集まりやすいミーティングスペースなど、業務内容に応じて自由に場所を選択できる「ABW(アクティビティ・ベースド・ワーキング)」の考え方も取り入れています。
もちろん、こうした働き方の大きな変化には、不安を感じる従業員もいると考えていました。「毎日座る場所が変わることに不安を感じる」「誰がどこにいるか分かりにくい」といったネガティブな側面もゼロではありません。
そこで、変化に伴う従業員の不安を払拭するため、フリーアドレスのメリットだけでなく、考えられる懸念点や対応策、他社のフリーアドレスに関する成功事例についても、研修で丁寧に説明する機会を設けました。
新しいオフィス環境によって、従業員の方の様子はどのように変化しましたか?
林様:日常的な交流が増え、組織の「心理的安全性」を高める上で大きな効果をもたらしていると感じています。
オフィスレイアウトの変更は、「どのようなオフィスにしたいか」を従業員の声を多く取り入れながら行いました。そのため、従業員が「自分たちの声が会社に届いて実現してもらえた」という実感につながり、以前よりも意見を言いやすい雰囲気になったようです。
また、仕事で接点のない他部署のメンバーと隣り合わせで仕事をしたり、気軽に相談したりする光景も増えました。
気軽に話す機会が増えたおかげか、「最近、あの人は元気がないよ」「挨拶してもあまり反応がなかった」といった声が総務部にも入りやすくなりました。メンタルヘルス不調の兆候は、「普段はどのような人なのか」を理解していないと、ささいな変化に気づきにくいものです。従業員同士の交流が増えることで、そうした不調の兆候にも気づきやすい環境が整いつつあると感じています。
「悩んでいるのは自分だけじゃない」ストレスチェックと研修から、安心感と前向きな意識を育む
ストレスチェック「Co-Labo」を導入いただいた経緯や導入後の感想について教えてください。
林様:法令でストレスチェックが義務化された当初から、紙でのストレスチェックを実施していましたが、配布や回収、集計に手間と時間がかかっていました。そこで、よりスムーズな運用を目指して電子化を検討していくなかで、リアルタイムで結果を確認できる「Co-Labo」を知りました。
設問のカスタマイズ性や、メンタルヘルス・ヘルスケア研修をセットで依頼できる点にも魅力を感じました。ストレスチェックを単なる法令対応で終わらせず、従業員の健康維持・改善につなげるための施策を、エムステージとなら相談しながら進められるのではないかと期待しました。
導入後は、管理部門の集計業務の負担が大幅に軽減されただけでなく、従業員からも「受検後、リアルタイムですぐに結果を見れる点が良い」と好評です。従業員自身の関心が高まり、研修などの次の施策にもつなげやすくなったと感じています。
ストレスチェックを「やって終わり」ではなく、研修を通じてメンタルヘルス対策を強化したいという思いがあったのですね。
林様:そうですね。従業員がストレスチェックの結果をただ確認するだけでなく、その意味を正しく理解し、セルフケアに活かしてほしいという思いがありました。
管理職向けには、1on1ミーティングの実践方法や、ラインケアの重要性といった、部下と関わる中でどのようなポイントに気を付ければ良いのかなど、より具体的な知識が必要だと感じ、セルフケアとラインケアをテーマにした研修をお願いしました。
矢崎様:また、ストレスチェックと並行してエンゲージメントサーベイも実施しているので、個人と組織の両面から健康状態や課題を可視化することで、研修のテーマ設定をするようにしています。
オフィス移転のように、会社の変化によって従業員にどのような影響がありそうなのか、今後顕在化し得る課題を先回りしてアプローチしていくことが必要だと感じています。
研修を実施してみて、従業員の方からはどのような反響がありましたか?
林様:「ストレスは誰にでも起こりうる」という共通認識が生まれたことで、「悩んでいるのは自分だけじゃない」という安心感につながったようです。ワークを通して、ストレスを「自分ごと」として捉える良い機会になったと思います。
ストレスを一方的にネガティブなものと捉えるのではなく、その仕組みを理解し、ポジティブに向き合おうという意識が育まれたと感じています。
矢崎様:研修の最大の効果は、従業員同士の対話と共感の機会が生まれたことだと感じています。特にグループワークでは、普段あまり話す機会のないメンタル面の悩みや意見を共有することで、安心感や共感が生まれて前向きな気持ちにつながったと、参加した私自身も感じています。
ストレスへの基本的な理解や、アサーションといった思考のクセなど、普遍的なテーマは継続的に今後も実施していきたいです。
多様な人材が相互理解を深められる組織を目指したい
今後取り組んでいきたいことがあれば教えてください。
矢崎様:当社は女性社員の比率が半数を超えており、女性が長く安心して働ける環境づくりも重要なテーマです。ただ、それは女性だけを特別扱いするということではなく、男性社員も含め、性別に関係なく誰もが協力し合える風土を育むことが大切だと考えています。「女性中心」ではなく、男性も含めて相互理解し合えるようなテーマも研修に盛り込んでいきたいです。
林様: 男女間の協力体制と同様に、より広い意味での「相互理解」の促進が重要だと考えています。弊社は新卒入社とキャリア入社の従業員がおよそ半々という構成でもあり、多様なバックグラウンドを持つ人材が集まっています。一人ひとりの個性を尊重し、互いの違いを理解し合える組織を目指していきたいです。